2025年10月、自民党総裁に高市早苗氏が就任したことで、日本経済に新たな注目が集まっています。
日経平均は心理的節目を超えるなど、投資家の期待感が広がりました。
2012年に安倍政権の時の政策として『アベノミクス』を実行しました。
安倍総理の意思を受け継ぐ政策をするのではないかということで、現在「サナエノミクス」があるのでは?!と就任直後から円安・株高が進行し、市場は熱気に包まれています。
そこでアベノミクスはどんな内容だったのか、どの業界が恩恵を受け、どこが逆風となるのかを整理していきます。
🇯🇵 アベノミクスとは何だったのか
安倍晋三政権の経済政策で3本の矢を掲げました。
| 政策の柱 | 内容 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 金融緩和 | 日銀による大規模な資金供給・マイナス金利導入 | 円安・輸出促進・株価上昇 |
| 財政出動 | 公共事業・地方創生などへの国費投入 | 雇用維持・景気刺激 |
| 成長戦略 | 規制緩和・企業支援・海外投資促進 | 民間主導の経済拡大 |
 トレーダーruka
トレーダーrukaアベノミクスは 2012年12月から約8年間続いた日本経済再生策 で、「株高・円安・企業収益拡大」を実行しデフレ脱却を目指しました。
アベノミクスの時系列
| 年 | 主な出来事 | 内容・政策の動き |
|---|---|---|
| 2012年12月 | 第2次安倍内閣発足 | 「デフレ脱却」「大胆な金融緩和」を掲げてアベノミクスがスタート |
| 2013年4月 | 黒田東彦氏が日銀総裁に就任 | 「異次元の金融緩和」開始(マネタリーベースを2年で倍増) |
| 2014年 | 消費税率5%→8%へ引き上げ | 景気刺激策と消費冷え込みの綱引き状態に |
| 2016年1月 | マイナス金利政策を導入 | 銀行の収益圧迫も進むが、円安・株高を後押し |
| 2018年〜2019年 | 海外投資・輸出拡大路線 | 外需依存が強まる一方、賃金上昇は限定的 |
| 2020年9月 | 安倍首相辞任(菅政権へ) | 約8年にわたる「アベノミクス時代」が幕を閉じる |



しかし、アベノミクスは実際には大成功だったわけではなく
1️⃣ 実質賃金が上がらず、庶民の生活が豊かにならなかった(株高は一部富裕層に偏った)
2️⃣ 日銀の金融緩和に依存しすぎて、財政健全化が進まなかった
3️⃣ 格差拡大と地方経済の停滞(都市だけが恩恵を受けた)
と一部が恩恵を受ける政策だったとも言われています。
💬 サナエノミクスとは
高市総裁の経済方針は、「積極財政」×「成長分野支援」に軸足を置いたもの。
つまり、アベノミクスの金融依存型から一歩進めて、「国家主導で未来産業を育てる」政策が特徴です。
高市総裁の政策まとめ
- 財政出動を継続し、国防・科学技術・エネルギー分野に重点投資
- 日銀の金融緩和は維持しつつも、金利引き上げには慎重
- 税制や補助金で国内産業の再構築を支援
- 「日本の技術と人材を守る」という保守経済的スタンス
これが投資家の間で“サナエノミクス”と呼ばれています。
📈 高市政権で「伸びる業界」4選
| 分野 | 概要 | 注目企業例 |
|---|---|---|
| 防衛・安全保障関連 | 防衛費の増額、装備更新など。景気に左右されにくい安定分野。 | 三菱重工業、川崎重工業、IHI、日本アビオニクス |
| インフラ・建設・不動産 | 積極財政による公共投資・都市再開発の拡大 | 大成建設、清水建設、鹿島建設、三井不動産 |
| エネルギー・原発・新エネ | 原発再稼働・水素・再生エネルギー政策の強化 | Jパワー、関西電力、三菱商事、日本製鋼所 |
| ハイテク・半導体(AI分野) | 経済安全保障の観点から半導体・量子・宇宙分野を強化 | 東京エレクトロン、レーザーテック、アドバンテスト、ソニーG |
⚠️ 一方で「逆風となる業界」4選
| 分野 | 理由 | 具体的影響 |
|---|---|---|
| 銀行・金融(特にメガバンク) | 金利引き上げに慎重姿勢 → 利ざや拡大が難しい | 低金利長期化で収益圧迫の懸念 |
| 円高メリット企業(輸入依存型) | 円安で輸入コスト増 → 利益率悪化 | 小売・食品・製造業に影響 |
| 内需小売・低価格業態 | 物価高と賃金停滞 → 消費者の財布の紐が固くなる | 利益率がさらに圧縮される |
| 借金体質企業 | 金利上昇局面で返済負担が増大 | 中小企業の資金繰り悪化リスク |
アベノミクスとサナエノミクスの違いは?
当時と決定的に違うのはインフレとデフレ
アベノミクスが始まった2012年当時、日本は長いデフレに苦しんでいました。
スーパーの食品や日用品の値段は下がり続け、人々は「まだ安くなるかも」と買い控える。
結果的に企業の売上も伸びず、給料も上がらないという悪循環が続いていたのです。
一方、今の日本はその逆。
物価が上がり続け、**生活コストだけが上昇している“悪いインフレ”**の状態です。
同じことを行なっても現在は世界の通貨バランスが大きく違うため、高市政権になった場合課題が山積みの状態です。



およそ10年前の日本はスーパーや家電量販店では「値下げ競争」「特売文化」が進み、企業もコスト削減を優先し、給料を上げられない構造になっていました。
物価の価値が低いため大量消費・大量生産するしかなかった時代です。
デフレとインフレのおさらい
| 比較項目 | インフレ(物価上昇) | デフレ(物価下落) |
|---|---|---|
| 物価 | 上がる(モノの値段が高くなる) | 下がる(モノの値段が安くなる) |
| お金の価値 | 下がる(同じ1万円で買える量が減る) | 上がる(同じ1万円で買える量が増える) |
| 消費行動 | 早めに買う傾向(将来値上がりするかも) | 買い控え(もっと安くなるかも) |
| 経済への影響 | 景気は活発化しやすいが生活コストが上昇 | 景気停滞・企業収益悪化・賃金も上がらない |
| 政策対応 | 金利を上げて物価を抑える(金融引き締め) | 金利を下げてお金を回す(金融緩和) |
| 代表的な時期 | 現在の日本(円安・値上げラッシュ) | アベノミクス初期(低物価・低金利時代) |



政策を実行するには為替、通貨、物価と賃金などバランスを正常化することが必須になります。
バランスが悪い中どちらかに舵を切ると歪みが生まれやがて格差が大きくなり二極化していきます。
💡香港が示す“インフレ社会の”光と影”
インフレは必ずしも「悪」ではありませんが、制御できないインフレは社会に深い分断を生み出します。
たとえば香港では、不動産価格の急上昇によって一部の富裕層しかまともな住宅を購入できない状況になりました。
金融や不動産で利益を上げる層が富を拡大する一方、一般市民は生活コストの上昇に追いつけず、「金融都市・香港」という成功の裏で、貧富の差という影が強くなったのです。
この構図は今の日本にも少しずつ重なってきています。
株式市場が史上最高値を更新する一方で、実際の生活では値上げや税負担が続き、資産を持つ人と持たない人の格差が拡大していきています。
✍️ 筆者のまとめ
アベノミクスの再来とも言われる「サナエノミクス」ですが、当時と今では日本経済の背景が大きく異なります。
かつて日本は「高品質で安い日本製」として世界中から支持されていました。
デフレ下で物価は安定し、真面目な日本企業の製品が高く評価されていた時代です。
しかし実際には一部の大企業だけが潤い、中小企業や労働者には恩恵が届きにくいという批判もありました。
さらに多くの企業がコスト削減を目的に中国など海外での生産にシフトし、結果的に技術やノウハウを国外に渡してしまいました。
これにより“日本ブランド”の価値が徐々に薄れたのではないかと感じます。
その後、菅政権・岸田政権へと受け継がれる中で、国民の実質賃金は伸び悩み、「豊かになったはずなのに生活は楽にならない」という声が増えていきました。
今は大量生産・大量消費の時代ではなく、本質的な「品質」や「独自性」が問われる時代。
高市政権が誕生し、本気で国内産業への投資や技術開発を支援していくなら、日本は再び世界に誇れるものづくり国家としての地位を取り戻せるはずです。
そして経済政策というのは、為替・通貨・物価・賃金のバランスが崩れると、どんなに株価が上がっても歪みを生みます。
日本でも同じように、株や資産を持っている人は恩恵を受けていますが、資産を持たない人の貯金はインフレによって実質的に目減りしています。
100万円の預金が70万円の価値になる——これが“静かな貧困”であり、経済の歪みの象徴です。
だからこそ、これからの日本には「一部が潤う経済」ではなく、「みんなが生きやすい経済」をつくる政策が必要だと思います。
高市政権がもし本気で国内産業を支援し、技術投資や雇用の循環を促すなら、日本は再び“安心して働ける国”に戻れるはずです。
経済の数字だけでなく、人々の暮らしの豊かさを取り戻すことこそ、次の時代に求められる本当の成長だと私は考えます。
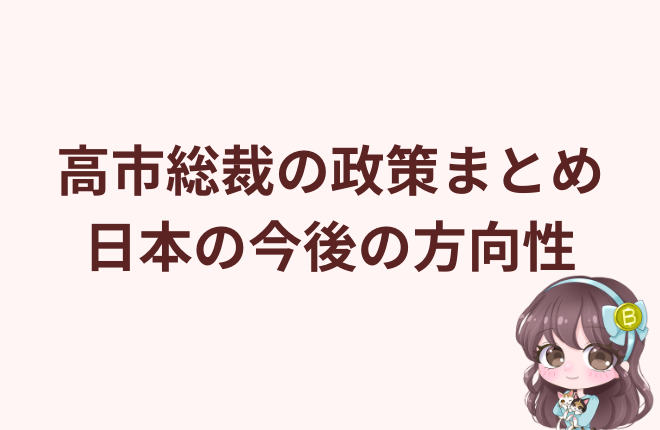
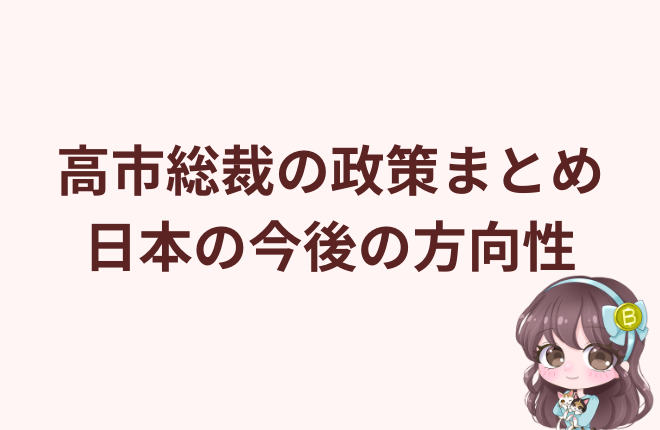


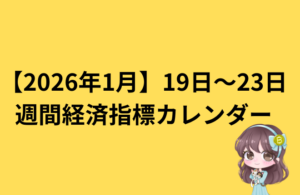
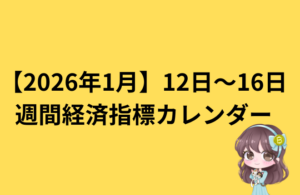
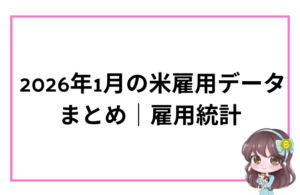
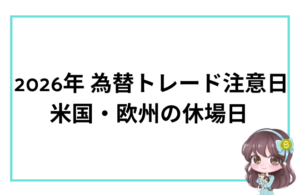
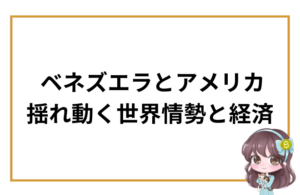
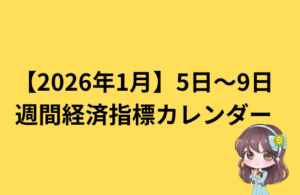
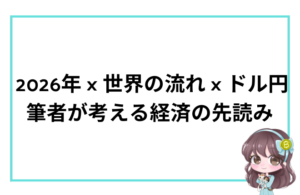
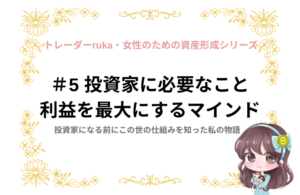
コメント