今週の注目ポイント
今週は、米FOMC議事要旨とミシガン大学消費者信頼感指数が最大の注目イベントです。
日本では家計調査、国際収支、企業物価指数(PPI)など、物価と消費の現状を示すデータが続きます。
10月6日(月)
★ スイス 失業率(9月)16:00
★★ ラガルドECB総裁 発言 26:00
★★ ベイリーBOE総裁 発言 27:30
週明けは欧州の中央銀行関係者の発言が中心です。
市場はインフレ鈍化ペースや利下げ時期に関するヒントを探る展開となりそうです。
10月7日(火)
★ 日本 家計調査・消費支出(8月・前年比)08:30
★ 日本 外貨準備高(9月)08:50
★ 日本 景気先行指数・一致指数(8月速報)14:00
★★ 米国 貿易収支(8月)21:30
★ 米国 消費者信用残高(8月)28:00
日本では家計支出や景気指数など、内需関連のデータが発表されます。
米国では貿易収支と消費者信用残高が公表予定ですが、政府閉鎖の影響で遅延の可能性もあります。
10月8日(水)
★ 日本 毎月勤労統計(8月)08:30
★★ 日本 国際収支(貿易収支・経常収支、8月)08:50
★★★ RBNZ(NZ中銀)政策金利 10:00
★★★ 米国 FOMC議事要旨(9月分)27:00
FOMC議事要旨では、9月会合での利下げ議論の詳細が注目されます。
特に「年内追加利下げ」や「中立金利の見直し」に関する文言が焦点です。
利下げペースに対する市場の織り込みが変化すれば、ドル円にも影響が及ぶでしょう。
10月9日(木)
★ 日本 対外・対内証券投資(週次)08:50
★★★ ECB理事会議事要旨 20:30
★★ 米国 新規失業保険申請件数(週次)21:30
週中盤は、欧州の議事要旨と米雇用関連データが焦点です。
労働市場の減速傾向が明確になれば、FRBのハト派姿勢が強まる可能性もあります。
ただし、米労働省が閉鎖対象となった場合、このデータも一時停止の可能性があるため注意が必要です。
10月10日(金)
★ 日本 国内企業物価指数(PPI・9月)08:50
★★ カナダ 雇用統計(9月)21:30
★★ 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報・10月)23:00
★★ 米国 財政収支(9月)27:00
週末は米国のミシガン大学指数と財政収支が予定されています。
特に財政収支については、政府閉鎖が長引けば発表延期の可能性があります。
経済データの欠落が市場の不透明感を高め、短期的なリスク回避姿勢を強める可能性があります。
まとめ
- 日本では家計調査や企業物価指数など、内需・物価動向が焦点。
- 米国はFOMC議事要旨・ミシガン指数など、景気減速と利下げペースを占う週。
- 政府閉鎖リスクが再燃しており、一部指標が発表中止または延期される可能性に注意。
- 指標発表が不透明な場合でも、市場は「期待・憶測」で動くため、ドル円・株式のボラティリティ上昇に要警戒。
- 自民党総裁に高市氏が就任したことで、日本の政権交代が現実化。
経済政策の転換や円安是正への姿勢が注目されており、新内閣の方針次第で円相場に変化が出る可能性があります。
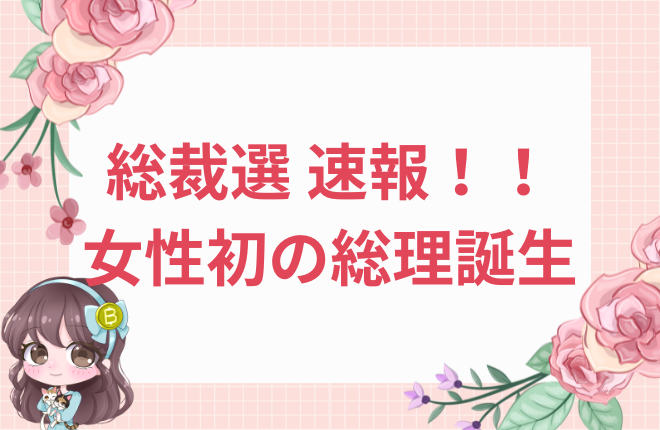
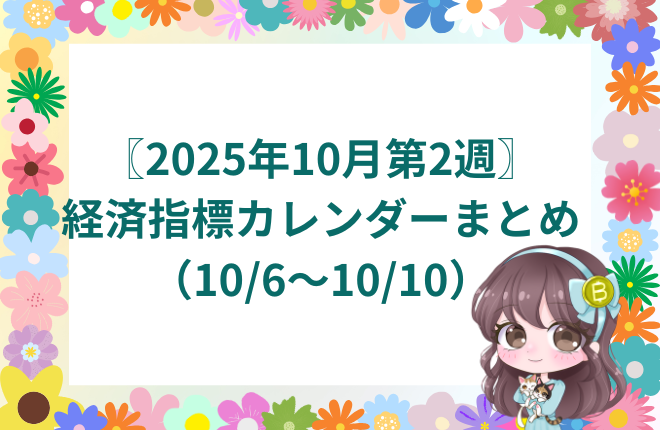
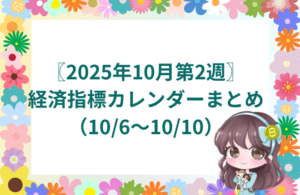
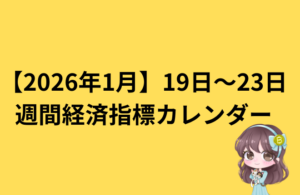
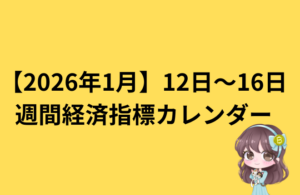
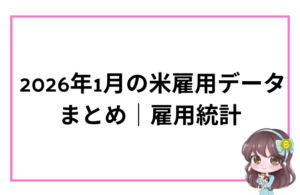
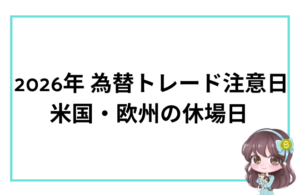
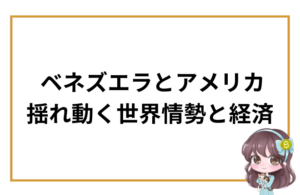
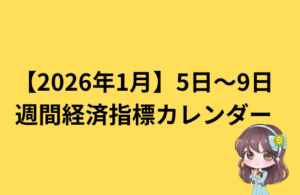
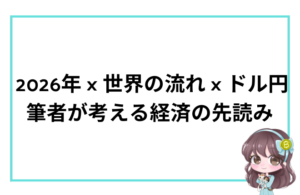
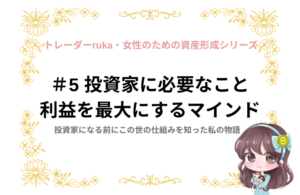
コメント