第1弾では「AIが仕事を奪う時代」について考えました。
もしAIが人間の代わりに働いてくれるなら、生活の保障はどうなるのでしょうか?
今回の記事では、ベーシックインカム(BI)の基本、実際に導入を試みた国や地域の事例、そしてAIが生み出す富とBIの関係について整理します。
さらに、働かなくても生きられる社会がもたらすメリットと課題を考えていきます。
 トレーダーruka
トレーダーruka数年前から話題になってるベーシックインカム(略BI)について改めて整理して考えてみましょう!
ベーシックインカムとは何か
ベーシックインカムの起源を深掘り
ベーシックインカムの考え方に近いものは、古代ローマですでに行われていました。
ローマ市民には無料で小麦を配給し、最低限の生活ができるように支援していました。
これは現代のBIの「すべての人に生きるための基礎を保障する」という思想と重なります。
現在のベーシックインカム導入例
世界ではいくつかの国や地域で実験的に導入が進められています。
- フィンランド:失業者に毎月560ユーロを支給 → 精神的ストレスが減り、幸福度が上昇
- カナダ(オンタリオ州):健康改善や生活安定が報告されたが、政権交代で途中終了
- アメリカ(カリフォルニア州ストックトン市):毎月500ドルの給付 → 就業率がむしろ上昇
これらの結果から、「働かなくなる人が増えるのでは?」という懸念よりも、安心して次のステップに進む人が増えるという傾向が見られます。


AI×ベーシックインカムの相性
AIは膨大な生産性を生み出します。
工場の自動化、物流の効率化、ホワイトカラー業務の代替により、社会全体の付加価値は増加します。
このAIが生み出した富に課税し、それを国民に再分配する形でベーシックインカムの財源が賄われる可能性があります。
つまり、AIが働き、得られた利益が私たちの最低限の生活を支えるという未来像です。
社会と人間への影響
ベーシックインカムが導入されると、次のような変化が予想されます。
- プラス面
- 貧困や生活不安が減り、精神的な安心感が増える
- 学び直しや新しい働き方に挑戦する人が増える
- 創造的な活動やボランティアが増加する可能性
- マイナス面
- 生きがいを失う人が出る(働くことがアイデンティティの人ほど影響大)
- 社会とのつながりが薄くなり、孤独感が増える可能性
- 財源問題(誰が負担するのか、国か企業か、どの税を上げるのか)
特に「虚無感と孤独」は深刻な課題です。
現役時代にバリバリ働いていた人ほど、定年後に生活の意味を見失いがちです。
AI時代のベーシックインカムは、この**「人間の存在意義」を再定義する仕組み**でもあるかもしれません。
現時点での課題
AI時代になると、ここに新しい視点が加わります。
AIやロボットが生み出す生産性向上分に課税する「AI課税」、大企業の超過利益に課税する「法人税強化」など、
“人間が働かなくても回る経済”を前提とした新しい財源モデルが議論されています。
しかし、現実的には課題も多いです。
- ロボットやAIの導入コストを国が負担するのか、企業が負担するのか
- 電気や半導体、メンテナンスなどAI維持コストをどう確保するか
- 社会的孤立や生きがい喪失を防ぐ仕組みをどう設計するか
これらの課題がクリアされない限り、ベーシックインカムは理想論にとどまる可能性もあります。
筆者のまとめ
ベーシックインカムは、単なるお金の配分ではなく、「人間はどうすれば平等に生きられるか」という人類が何百年も考え続けてきたテーマの集大成だと思います。
トマス・ペインの時代から議論され、現代ではAIという新しい要素が加わり、いよいよ現実的に検討される段階に来ています。
最低限の生活が保障される未来は、確かに近づいていると感じます。
ただし、財源や制度設計、社会とのつながりをどう維持するかといった課題はまだ残っています。
次回は、人間にしかできないこと──体験、経験、ゼロから1を生み出す力──について一緒に考えていきましょう。
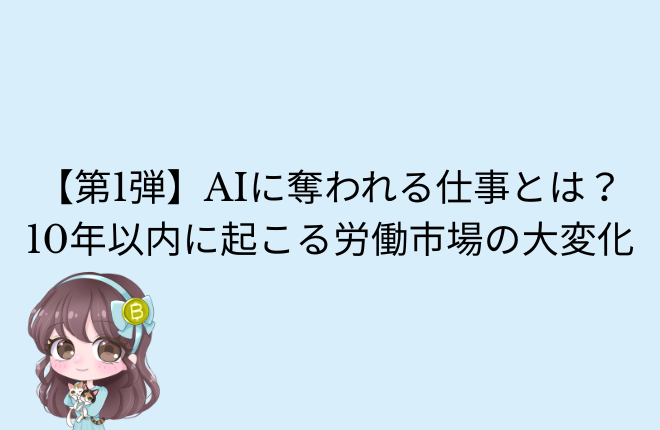
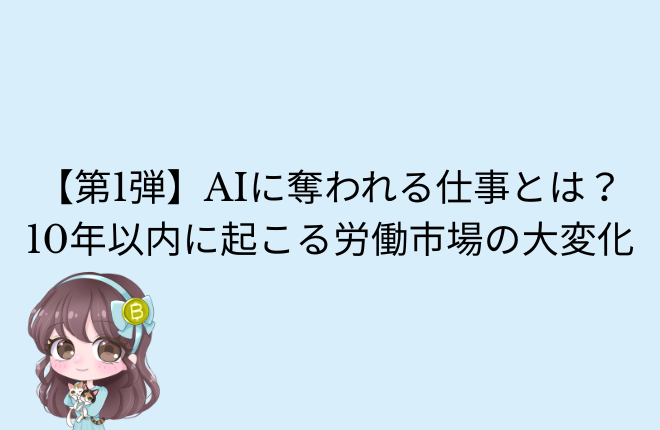
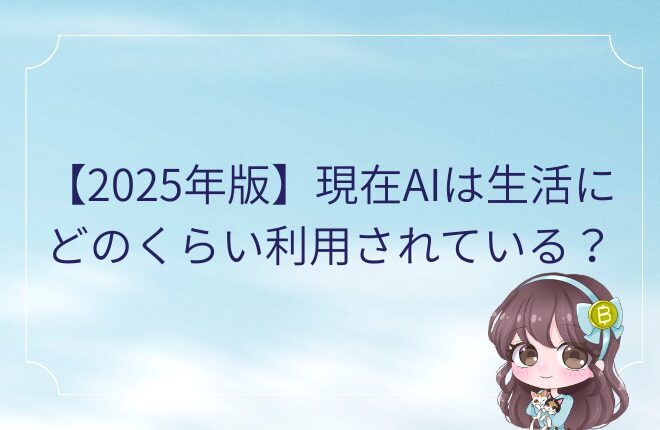
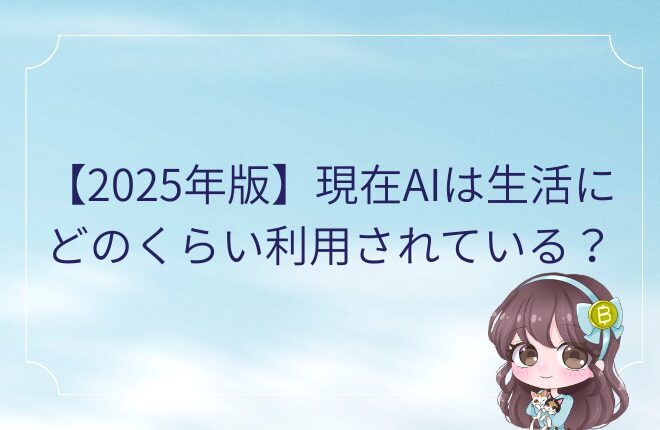
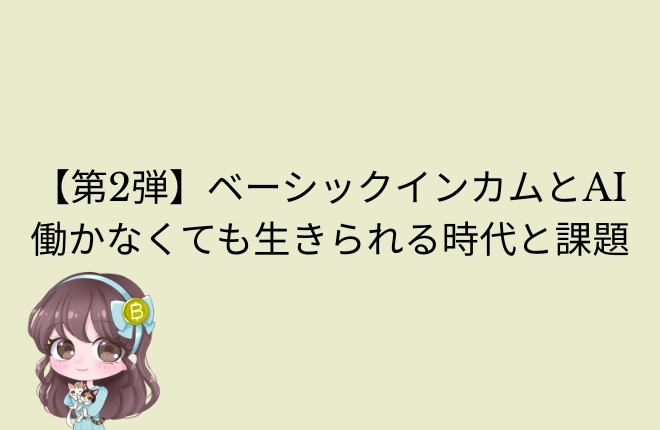
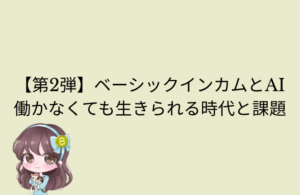
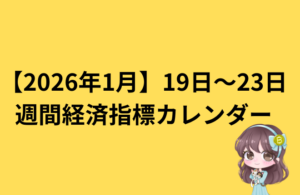
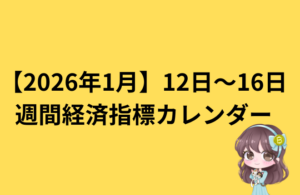
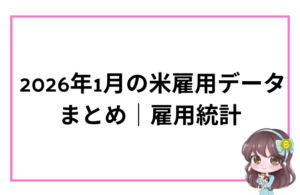
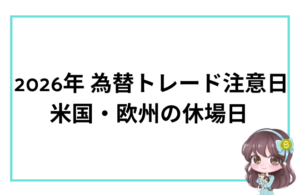
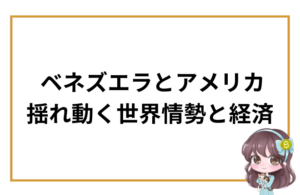
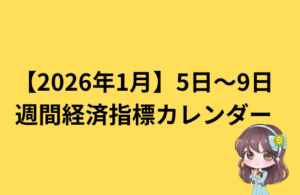
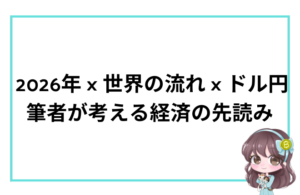
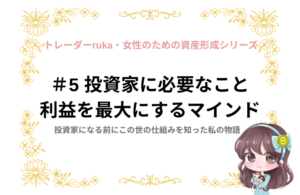
コメント