生活の中で感じる「物価上昇」
スーパーで買う卵、牛乳、パン。
気づけば「あれ、また値上がりしてる?」と思う瞬間が増えていませんか?
これがニュースでよく聞く「物価上昇」、そして経済用語でいう「インフレ」です。
でも「インフレ」と聞くと、難しそうな経済の話に感じるかもしれません。
そこで今日は、具体的にわかりやすく物価の上がり方と為替(ドル円)の関係を、過去の動きと生活への影響を交えて解説します。
 トレーダーruka
トレーダーrukaコンビニのおにぎりが100円だった頃なんて昔の話じゃありません、、、たった4年で安くても180円くらいします泣
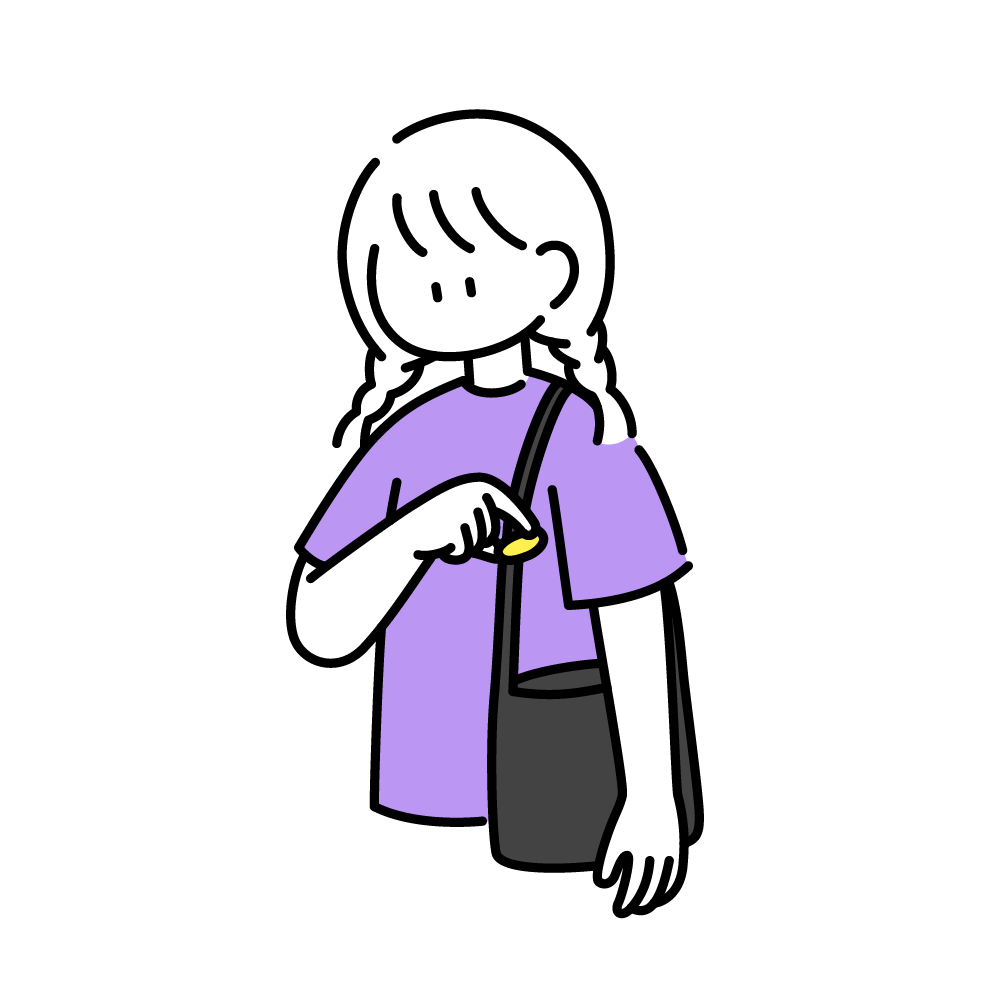
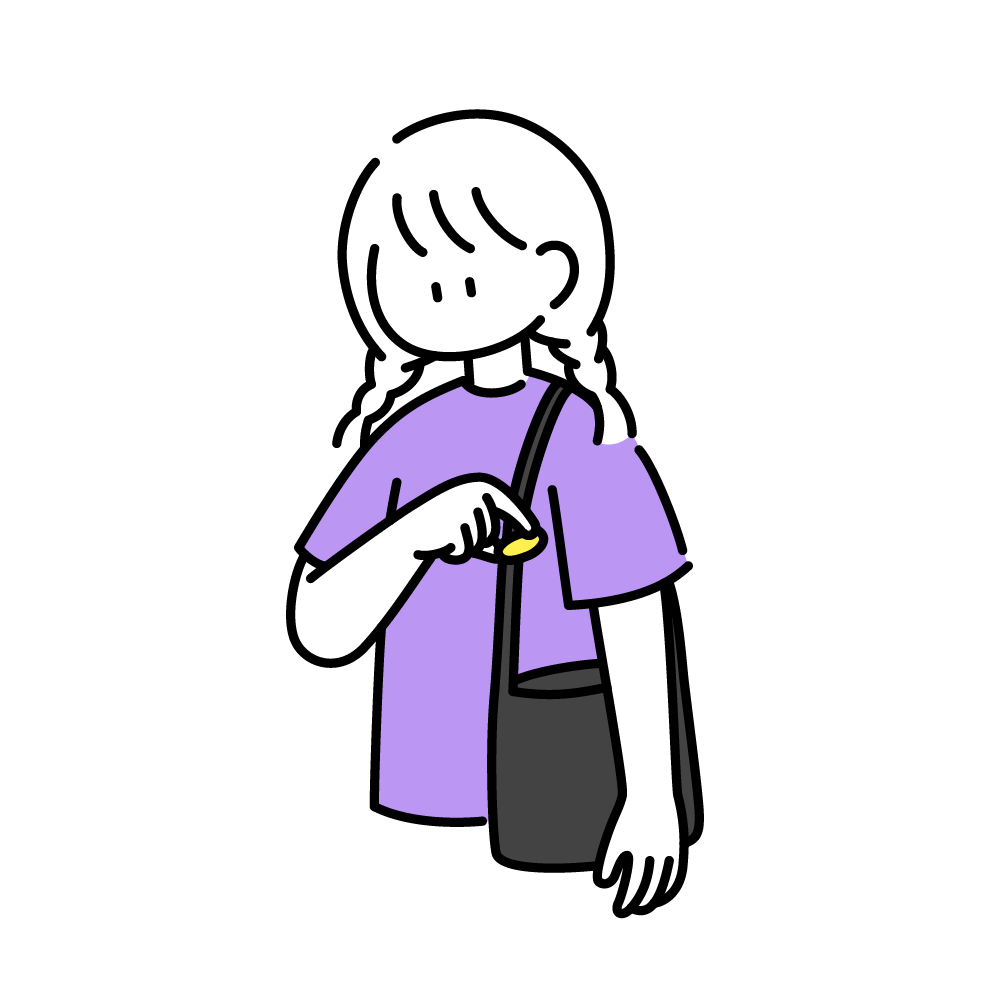
インフレって、実際どういう意味?
例えば、去年まで100円で買えたパンが今年は120円になった場合、同じお金で買える量が減ります。これがインフレの本質です。
ポイントは2つ
- お金の価値が下がる(同じ金額で買えるものが減る)
- 物価が上がる(値段が高くなる)
適度なインフレは経済の活発さを示すこともありますが、日本のように賃金上昇が遅い国では、インフレは生活コストの上昇を意味します。
物価上昇で減る「お金の実質的な価値」
例えば、2020年に100万円を銀行口座に置いていたとします。
その間、日本の物価(消費者物価指数)は年平均でおよそ2〜3%ずつ上昇し、2022〜2023年は食品やエネルギー価格が急騰しました。
2020年を基準にした場合、
- 2020年 → 100万円
- 2025年現在 → およそ92〜94万円の価値
つまり、物価が上がると同じ100万円でも買えるモノやサービスの量が減りお金の価値は確実に目減りしているのです。
生活感で置き換えると
- 2020年に1パック150円だった卵 → 2025年には250円超え
- 100円で買えた菓子パン → 120〜140円に
- ガソリン1リットル → 130円台 → 170円台
こうした積み重ねで、感覚的には財布の中身が1割減ったような状態になります。
だからこそ、物価上昇(インフレ)時はお金をただ貯金するだけではなく、価値を守る運用や分散が必要になるわけです。



もうみんな生活で実感しているよね。すぐに100円のものが150円にならなくてもじわじわ物価は上昇してきてやっと身に染みてお金が減っていることに気づいてきてると思う。
過去10年の物価上昇とドル円の関係
2010年代前半
- 物価はほぼ横ばい。卵は1パック150円前後、ガソリンも安定。
- 為替は1ドル80〜100円台、円高傾向もあり海外旅行は割安でした。



日本は1990年代から約15年間、物価がなかなか上がらない「デフレ」に苦しんできました。その間の平均インフレ率は –0.3%と、微弱な物価の下落が続いていたのです。
そして2012年に首相に返り咲いた安倍晋三氏は、経済再生とデフレ脱却を掲げた「アベノミクス」を推進しました。
デフレは「安く買えて嬉しい」状態が長く続くように見えて、実は経済全体の元気がなくなり、給料や雇用にも悪影響を与える現象です。
2020年頃(コロナ禍)
- 世界的な物流停滞で一部商品がじわっと値上がり。
- 為替は1ドル105円前後で推移、大きな動きはまだなし。
コロナ禍に世界中で政府はお金を刷り給付や手当を配りました。そして、そこからじわじわとインフレが進んできました。お金の量が増える=インフレ加速とはそういうことでしょうか。解説します。



なぜ「お金をたくさん刷らなきゃいけなかった」のか
コロナ禍で世界中がロックダウンや行動制限をした結果
企業が営業できず収入がゼロになる
多くの人が仕事やパートを失い収入が減る
観光・飲食・交通などの業界が壊滅的な打撃
このままでは失業・倒産の連鎖が広がり、景気が崩壊してしまうため
各国政府は
現金給付(個人向け)
補助金や無利子融資(企業向け)
税金の減免や猶予を一斉に行いました。
その原資となるお金を国債発行や中央銀行の金融緩和(事実上のお金の増刷)で賄ったわけです。
同時に、コロナ禍で供給(モノを作る・運ぶ力)が大幅に低下しました。
- 工場の稼働停止
- 国際輸送の停滞
- 原材料の不足
つまり、
- 需要(お金を持って買いたい人)=急増
- 供給(売り物の量)=減少



お金は増えたのに物は足りない、、、
需給バランスの崩れが世界的に発生しました。
この結果、モノの価格が上がる=インフレが加速したのです。
2022〜2023年(エネルギー高騰)
- ガソリン・電気代・食品全般が急上昇。卵は250円超えも。
- 米国は物価8%台、日本は3%台。金利差でドル円は150円突破。
2022年から急速にエネルギー価格が上がりました。電気代が高騰したのも記憶にあるのではないでしょうか。
この頃、何が起きたのか解説していきます。



ロシア・ウクライナ戦争の勃発
2022年2月、ロシアがウクライナに侵攻
世界はロシアへの経済制裁を実施(金融・貿易・エネルギー取引制限)
ロシアは世界有数のエネルギー輸出国で、特にヨーロッパやアジア諸国への依存度が高かったのです。
2カ国が持つ主なエネルギー
ロシア🇷🇺
- 原油(世界第2位の輸出量)
- 天然ガス(世界第1位の輸出量、パイプラインで欧州へ)
- 石炭(日本も輸入)
ウクライナ🇺🇦
- 農業資源のイメージが強いが、天然ガスの輸送ルートとして重要
- 旧ソ連時代からのパイプラインが欧州へ続く中継地
- 一部原油・石炭も産出
日本はエネルギー自給率がわずか約12%(2021年)と低く、輸入依存度が非常に高い国です。
ロシアからは以下を輸入していました。
下記は2021年データです。
- 液化天然ガス(LNG):輸入全体の約9%
- 石炭:輸入全体の約11%
- 原油:輸入全体の約4%
特にLNGは発電用燃料として重要で、北海道・東北・関東の一部電力会社がロシア産に依存していました。



戦争でエネルギーが世界的に足りなくなり、日本も高い値段で買わざるを得なくなりました。
そのコスト上昇が電気代・ガソリン代からスーパーの値札まで広く響き、インフレを加速させました。
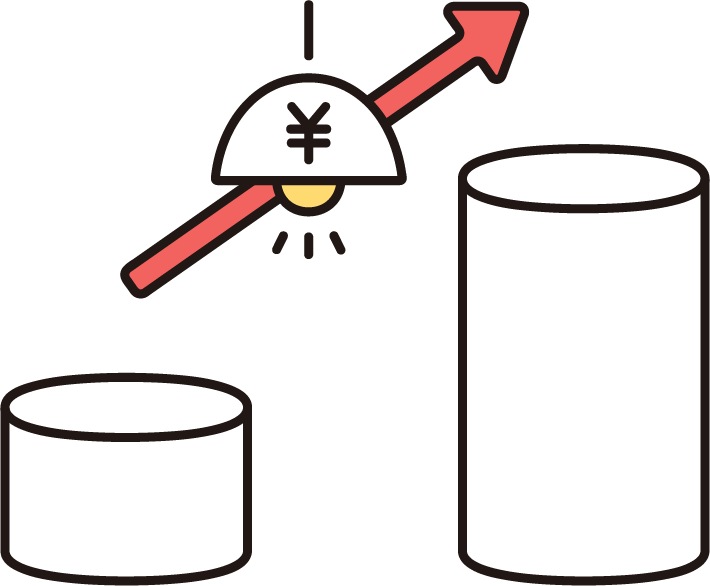
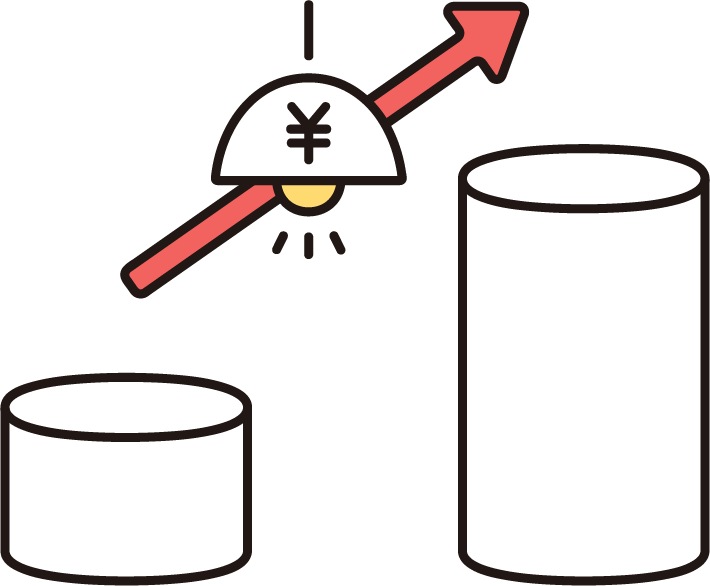
なぜ物価が上がると為替が動くのか
物価が上がると、多くの国はインフレを抑えるため金利を引き上げます。
しかし日本は利上げを先延ばしにして世界から政策に遅れを取りました。詳しく解説していきます。
1. 物価上昇と為替の基本的な関係
- 物価が上がる(インフレが進む) → 中央銀行はインフレを抑えるため金利を引き上げる
- 金利が高い国の通貨は買われやすくなる(投資家は利息が高い通貨を好むため)
- その結果、金利引き上げを行った国の通貨は**上昇(通貨高)**しやすい
2. アメリカと日本の為替に対する構図
- アメリカ
- 物価上昇 → FRB(米連邦準備制度)は迅速に利上げ
- 2022〜2023年にかけて急ピッチで利上げし、政策金利は5%以上に
- 高金利のドルは買われやすくなり、ドル高傾向
- 日本
- 日銀は長年、低金利・ゼロ金利政策を継続
- 物価上昇(2022〜2023年のエネルギー高騰期でも)でも利上げに消極的
- 金利差が拡大し、円は売られやすく円安傾向に
3. 現在(2025年時点)の見方
- アメリカ
- 2024年後半からインフレはやや鈍化傾向
- 市場は「利下げは近い」と予想しているが、労働市場の強さ次第では利下げが遅れる可能性あり
- ドル高基調は弱まりつつあるが、金利水準は依然として高い
- 日本
- 日銀は緩やかな金利正常化を議論しているが、急な利上げは見込み薄
- 物価は2%前後で推移(食品・サービス価格は高止まり)
- 結果として金利差は依然大きく、円高に反転するには米国の利下げが不可欠



ここで日本が利上げに踏み込まないとさらにインフレが加速します。なぜか日銀の植田総裁はハト派MAXですが、このままだと国民の生活は苦しくなります。
今夜のCPIがかなり注目されている
今夜のCPI(消費者物価指数)発表が生活に与える影響
2025年8月12日(火)本日の21:00、アメリカの物価データが発表されます。
雇用統計の大幅修正から1週間経ち相場の方向感が定まっていません。
本日アメリカにとって悪材料が出たら一気にドルが売られる、市場はアメリカ景気後退と判断し大暴落になりかねません。
もし予想より物価上昇が強ければ、ドル高円安が進み、輸入品・ガソリン代・海外旅行費がさらに高くなる可能性があります。
CPI前回の結果と今回の予測について
- 6月のCPI(前年同月比):+2.7%
→ 前月の+2.4%から上昇。コアCPI(食料・エネルギーを除く)は+2.9%に。経済調査サービス+2Bureau of Labor Statistics+2 - 7月のCPI予想:+2.8%
- 月次変動(前月比):予想+0.2%
- コアCPI(月次予想):+0.3%
- コアCPIの前年比見通し:最大+3.1%ReutersInvestopediaBusiness Insider



今夜のCPIの見方として下記が挙げられます。
緩やかなインフレ傾向:CPIは依然としてFRBの目標(2%)を上回っており、金融政策にも影響を及ぼす可能性が高い。
コア(基調)インフレの警戒感:コアCPIが+3%水準となると、インフレの持続性への懸念が強まり得る。
為替・市場への影響:「予想超えのCPIはドル高・金利据え置き観測への圧力」、「予想下回れば利下げ期待が高まる」
参考リンク
最新の米CPI予想については Reutersの記事 でも詳しく解説されています。
筆者のまとめ
前回の雇用統計では大幅な下方修正が入り、アメリカ経済への信頼感に揺らぎが生まれました。
そして今夜のCPI。もし今回の物価指数が予想を下回れば、景気後退(リセッション)や早期の利下げ観測が一気に強まるでしょう。これは株式市場にとっては一時的な追い風になる可能性もありますが、同時に全面安の引き金にもなりかねません。
逆に、予想を上回る結果となれば、インフレ加速への懸念が再燃し、アメリカの金融政策が再び引き締め方向に傾く可能性があります。いずれにしても、今回のCPIは「これからのインフレの行方」を示す重要な指標です。
物価や為替は、投資家だけでなく、日々の生活に直結するテーマです。ガソリン代、電気代、スーパーの食材の値札…それらはすべて世界経済の動きとつながっています。ニュースで数字を見ても「自分には関係ない」と感じるかもしれませんが、その数字があなたの家計を変えていくのです。



だからこそ今日のCPIの結果をきっかけに、これからの生活や資産の守り方について、少しだけ意識を向けてほしいと思います。


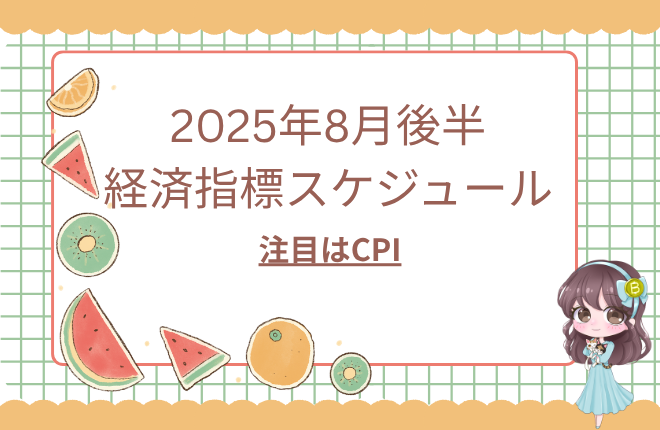
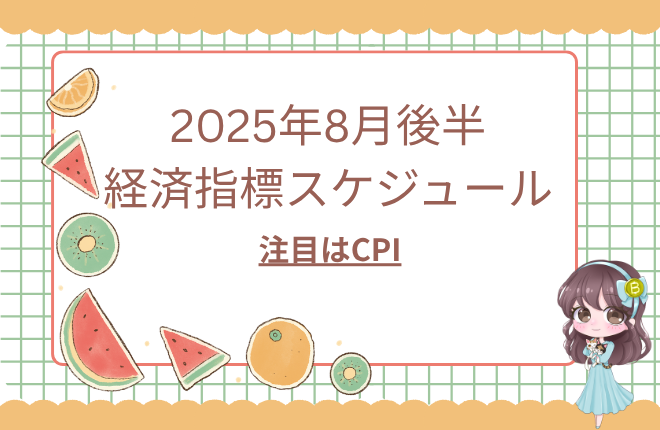
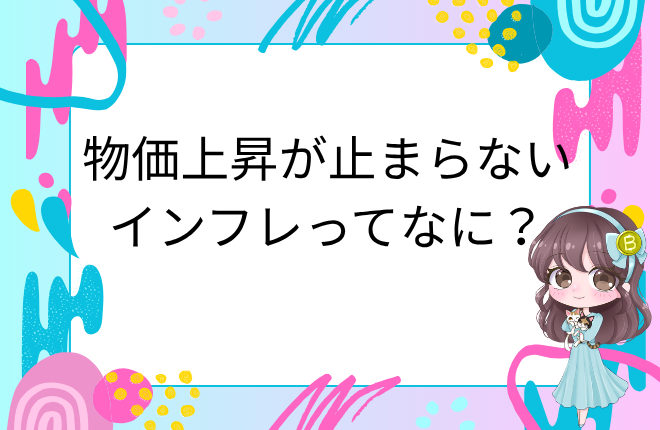
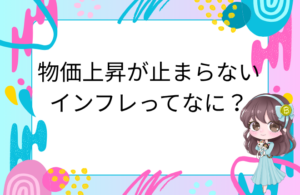
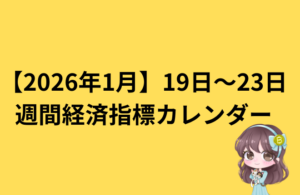
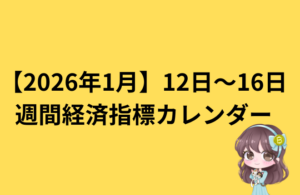
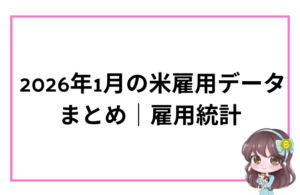
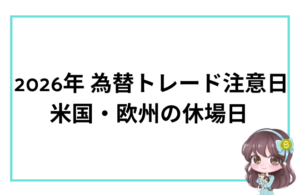
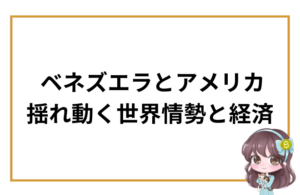
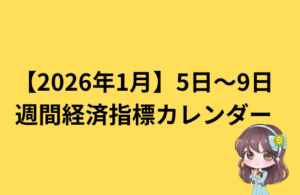
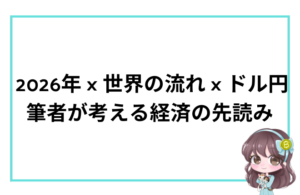
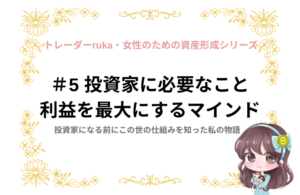
コメント