これまで第1弾では「AIに奪われる仕事」、第2弾では「ベーシックインカムとAIの未来」について書いてきました。
今回はシリーズ第3弾として、AIが進化する時代に人間にしかできないことは何か? というテーマを掘り下げます。
ChatGPTをはじめとするAIは一見、話し相手になったり、生活を便利にする存在になりつつあります。
しかし現実には、AIは「自分の会話を肯定するように設定することもできる」ため、誤情報や根拠のないまま会話が成立してしまうこともあるのです。
つまりAIが本当に代替できる領域と、人間にしか生み出せない付加価値の領域ははっきり分かれ始めています。
この記事では、その違いを整理しながら現時点で「AIにはできないこと」「人間にのみ備わっている能力」について考えていきます。
❶体験・経験の価値
AIは過去の膨大なデータを処理し、情報を提供することに長けています。
しかし実際に「体験する」ことはAIにはできません。例えば
- 旅先で見た景色の美しさ
- 誰かと過ごした時間の温かさ
- 失敗や挑戦から得た学び
こうした体験や経験に基づいた記憶や五感こそが、人間にしか持てない資産です。
この「一次体験の蓄積」からこそ、新しいアイデアや発想が生まれます。
❷ゼロから1を生み出す創造性
AIは「既存の情報を組み合わせて最適化」するのは得意ですが、ゼロから1を生み出し、効率のいいアイディアや斬新な提案は人間の方が長けています。
- まだこの世にないアートや音楽を制作する
- まだ存在しないビジネスモデルを立ち上げる
- 誰もやったことのない発想に挑戦する
こうした「はじまりの一歩」は、人間の想像力や直感から生まれます。
AIはその後を補助して効率化してくれますが、最初の種をまく役割は現時点で人間にしか担えません。

❸時間を共有し生まれる感情や信頼関係
人間同士の関係で大切なのは「時間を共有すること」です。
一緒に時間を過ごして、同じ出来事を繰り返し経験し、互いの反応を見ながら信頼を積み上げていく。それが「安心感」や「本当に分かり合っている感覚」を生みます。
AIは、会話を肯定してくれて心地よくするように設定できたり、過去の対話を参照できる場合もありますが、時間をかけて育む「連続した記憶」やそこから生まれる感情の整理・解釈を人間と同じようには行えないという現実があります。
たとえば:
- AIはアップデートやセッションの切り替えで以前の会話の文脈がリセットされることがある。
- 設定やプライバシー方針により、継続的に個人の記憶を蓄積して参照できずその内容を話し合うことができない。
- 一貫した時間の流れの中で「過去の出来事 → 感情の変化 → 現在の判断」に基づく深い洞察を出すのは難しい。
その結果、AIは確かに会話を肯定したり、共感するような言葉を返してくれますが、それは往々にして“その場の反応”であり、過去の積み重ねから生まれる“本当の理解”や“信頼に基づく提案”とは異なります。
人間は時間をかけて相手の背景や小さな変化を読み取り、それを踏まえて言葉を選び、次の行動や新しいアイデアを生み出します。
こうした「記憶→整理→創造」のプロセスは、現時点のAIにはまだ追いつきにくい領域です。
つまり、AIが「心地よい聞き手」にはなれても、時間と経験を共有して感情を整理し、深い信頼関係に基づく新しい発想をともに作るのは人間にしかできないという点が、これからの人間の大きな付加価値になります。
筆者のまとめ
ここまでを踏まえて、私の中では大きく2つの方向性が見えてきました。
1つは 日本が生き残る道、もう1つは 人間が生き残る道 です。
日本が生き残る道
日本には四季や美しい自然、文化、食といった他国にはない魅力があります。
AIでは提供できない「体験」と「感動」を与えられるのは観光業です。
だからこそ、これからの日本が注力すべきは観光業だと考えます。
観光とAIをうまく組み合わせ、未来を想像させるようなサービスに投資することが、日本の成長のカギになると思っています。
人間が生き残る道
人間にしかできないこと、それは「体験や感情を基にした付加価値の提供」です。
前に触れたピンクカラー(接客業)のように、お客さんの感情を汲み取り、個別の提案をするのはAIには難しい領域です。
例えばネイリストの仕事。
一時期は「AIによる自動プリントネイルで職業が消える」と言われましたが、結果的に流行せず、今はむしろネイリスト不足が続いています。
これは、人の手でしか提供できない繊細な施術や、爪の健康状態を判断する柔軟さが必要だからです。
同じように、人間の感覚や経験が求められる分野は多く残っています。
最後に
AIはデータ処理や機械的な動作を担う存在へと進化していきます。
だからこそ、わたしは「人間にしかできないこと」にフォーカスして生きることが大切だと思います。
投資先を選ぶときも、教育の方針を考えるときも、
「体験・創造・共感」という人間の付加価値を軸にすることが、これからの時代を生き抜くカギになると私は考えます。
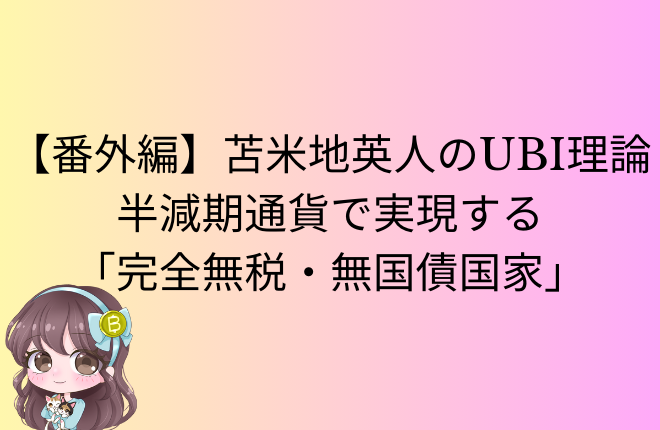
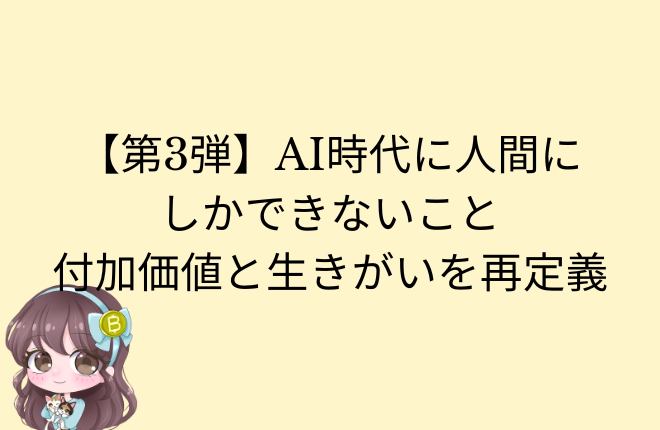
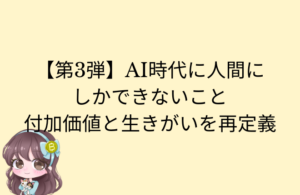
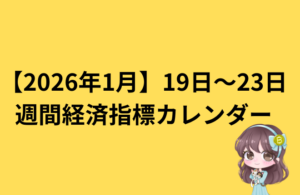
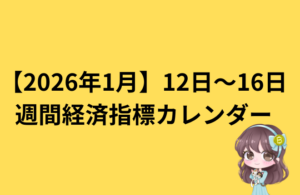
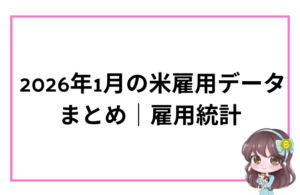
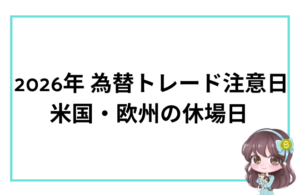
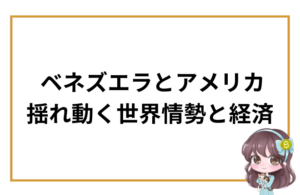
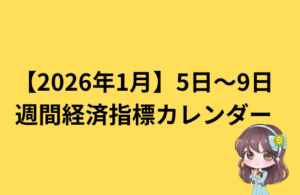
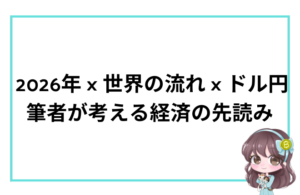
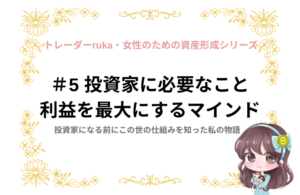
コメント