米FOMCは日本時間9月18日午前3時に政策金利を0.25%引き下げることを決定しました。
パウエル議長は会見で「急いで緩和するつもりはない」と述べ、利下げは始まったものの今後は慎重に判断していく姿勢を示しました。
発表内容
- 利下げ:基準金利を0.25%ポイント引き下げ。フェデラルファンド金利の新レンジは 4.00~4.25%。Investopedia+2Reuters+2
- 投票結果:多数決で利下げ決定。1名(Stephen Miran氏)がより大きな利下げ(0.50%)を希望したものの、全体では0.25%の利下げが採用された。AP News+2連邦準備制度理事会+2
- インフレ・雇用状況:雇用成長が鈍化、失業率がやや上昇。
- 物価(PCEインフレ)は依然として2%目標を上回る水準、特にコアインフレの高止まりを警戒。AP News+3連邦準備制度理事会+3Reuters+3
マーケットの反応
0.25%利下げの市場インパクト
0.25%(25bps)の利下げは、金融政策としては「小幅な調整」の部類です。
- 金利市場(債券)
即座に短期金利が下がるため、短期債は価格上昇(利回り低下)。長期債はインフレ見通し次第で逆に利回りが上がることもあり、必ずしも一方向ではない。 - 株式市場
基本的には「金利低下=企業の借入コスト減」でプラス要因。ただし今回は「景気減速懸念が背景」での利下げなので、ポジティブ材料として素直に株高になりにくい。 - 為替市場(ドル円)
理論上は「金利差縮小=ドル売り・円買い」の圧力。ただし市場は事前にかなり織り込んでいたため、サプライズ感が薄く反応は限定的になる傾向。
🔍 年内利下げ予測の内容
| 情報源 | 利下げ回数予想 |
|---|---|
| FOMCの「ドットプロット」(FOMC参加者の予測) | あと2回利下げ(10月と12月がメイン候補) Fox Business+2ヤフーファイナンス+2 |
| Barclaysの見方 | 年内で 3回の利下げ の可能性も見込まれている Investing.com |
| CME FedWatch(市場予想) | 年末時点で利下げが複数回入るという見方が市場に強く織り込まれてきており、3回ほどという期待が高まっている Beansprout+1 |
⚠️ 見通しに含まれる条件・リスク
利下げが入るとしても、以下の条件やリスクがクリアされなければ動きにくい:
- 雇用データ(失業率、新規雇用など)が「予想以上に悪化」すること
- インフレ指標(特にコアインフレ)が2%近辺へ継続的に収まる/鈍化の証拠が定着すること
- 経済の減速が明確になり、FRBとして「利下げを始める正当性」が議会・市場ともに受け入れられること
また、1回の利下げの大きさ(25ベーシスポイントが標準)や、どの会合で実行されるかによって、予想通りにはいかない可能性も高いです。
将来の経済見通し
- 2025年末までの追加利下げ:あと2回程度の利下げが見込まれている。レイモンド・ジェイムズ+2ファイナンシャル・タイムズ+2
- 経済成長率の予想:2025年の成長は約 1.6% の見通し。2026年以降はやや上方修正されてきている。レイモンド・ジェイムズ+1
- 失業率予想:2025年末にかけて若干の上昇を見込み、その後は緩やかに改善する見通し。レイモンド・ジェイムズ+1
筆者のまとめ
今回の0.25%の利下げは、正直市場を大きく動かすほどのインパクトはありませんでした。
それでもパウエル議長の発言からは「市場を混乱させないように、非常に慎重に利下げを進めていく」というスタンスが感じられました。
今後も年内に2〜3回の利下げが織り込まれており、実際に追加利下げが行われる可能性は高いと見ています。
ただ、雇用や失業率が改善するまでは相場の不安定さは残り、景気減速と金利低下が続く中で、ドルの基軸通貨としての力が徐々に弱まる兆しも見えてきたと感じます。
今回の利下げは、単なる一回の金融政策ではなく、世界経済の大きな変化の前触れかもしれません。
今後も雇用統計やインフレ指標を注視しながら、次の利下げ局面と世界の通貨バランスの変化を冷静に見極めていきたいと思います。
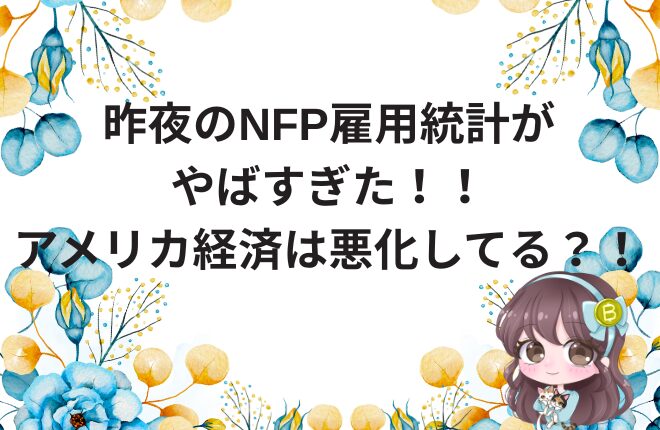

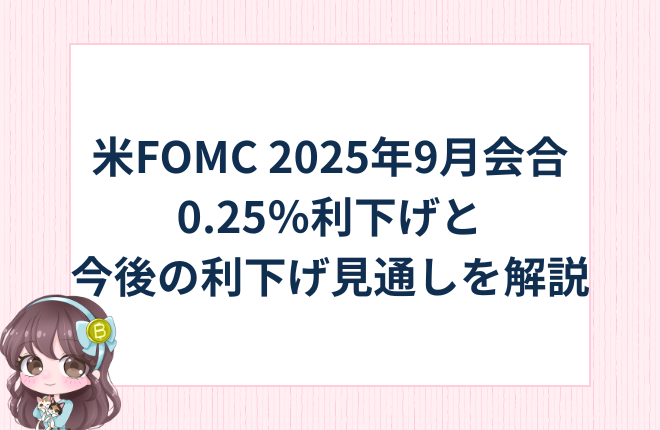
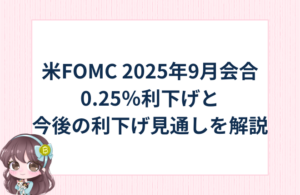
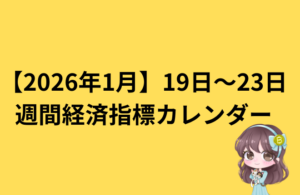
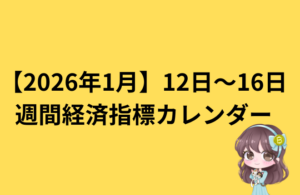
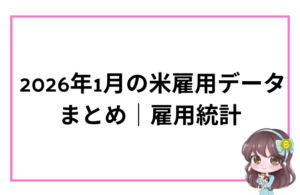
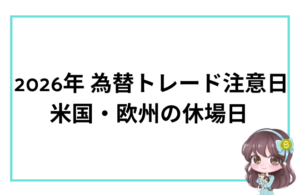
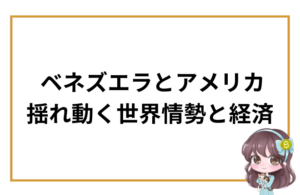
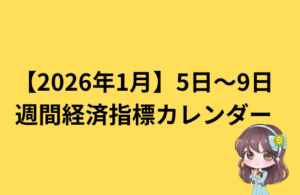
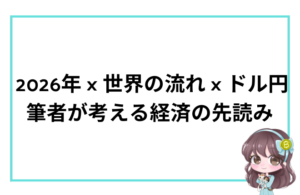
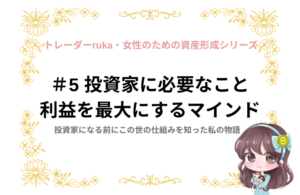
コメント