昨夜、日本時間23時ごろに発表された米国の年次雇用統計の改定(ベンチマークリビジョン)。
速報での雇用増が大幅に下方修正され、「実際の雇用環境は想像以上に弱かったのでは?」という懸念が再燃しています。
この記事では、今回の改定結果と過去の傾向、そして今の雇用状況について整理して振り返ります。
今回の年次改定の結果とその意味
2025年9月9日、日本時間23時ごろに発表された米国の**年次雇用統計改定(ベンチマークリビジョン)**は、投資家に強烈なインパクトを与えました。
米労働省統計局(BLS)は、2024年4月から2025年3月までの1年間の雇用増加が、実際には91万1,000人も過大計上されていたと発表。
これは統計の歴史の中でも最大規模の下方修正となります。
特に打撃が大きかったのは、娯楽・宿泊業(▲17.6万人)、専門・ビジネスサービス(▲15.8万人)、小売業(▲12.6万人)といったセクター。
景気を支えるはずのサービス業で想定以上に雇用が弱まっていたことが浮き彫りになりました。
2025年1月〜8月の雇用統計(速報ベース)
では、直近の雇用統計はどう推移していたのでしょうか。以下は今年の速報値です。
| 月 | 雇用増(前月比・速報) |
|---|---|
| 1月 | +24.5万人 |
| 2月 | +19.8万人 |
| 3月 | +21.0万人 |
| 4月 | +15.7万人 |
| 5月 | +7.5万人 |
| 6月 | +6.8万人 |
| 7月 | +7.3万人 |
| 8月 | +2.2万人 |
年初は20万人超の増加を維持していましたが、5月以降は一気に失速。特に8月はわずか+2.2万人と、実質的に「雇用の伸びが止まった」と言える数字です。
一見すると「まだプラス」と思えるかもしれませんが、今回の年次改定が示した通り、速報値は後から大きく修正されるリスクがあります。つまり、足元の雇用も本当はもっと弱い可能性があるのです。
年次改定の仕組みと見方
ここで「年次改定って何?」という疑問に答えておきましょう。
- 毎年9月に発表
- 対象期間は前年4月〜当年3月の12か月間
- 毎月速報で発表される「事業所調査(CES)」を、より網羅的な「雇用保険税記録(QCEW)」に置き換えて補正
今回の場合、2024年4月〜2025年3月のデータが見直され、「実際は91万人分の雇用が存在しなかった」と判明したのです。
つまり、今年1〜3月の雇用が+20万人前後と発表されていても、将来的に修正で大幅に削られる可能性があるということ。
今回の年次改定が信頼性を揺るがせたことで、市場は今後のNFP発表も「本当に正しいのか?」と疑う目で見るようになるでしょう。
過去の年次改定と傾向(2018〜2025)
| 期間(4月〜3月〆) | 改定幅(雇用数) | 概要 |
|---|---|---|
| 2018〜2019年 | ±数十万人規模 | 通常の修正幅(全体の0.2%程度) |
| 2019〜2020年 | 小幅修正 | コロナ直前で大きなズレなし |
| 2020〜2021年 | 下方修正 | コロナショックによる急減で調整幅が拡大 |
| 2022〜2023年 | −81.8万人 | コロナ後の反動で過大評価分を修正 |
| 2023〜2024年 | −59.8万人 | 下方修正続く、労働市場は弱含み |
| 2024〜2025年 | −91.1万人 | 過去最大の下方修正(今回発表) |
👉 コロナ以降、年次改定は下方修正が常態化しています。つまり、速報値の雇用統計は一見「堅調」に見えても、後で大きく下げられることが繰り返されているのです。
 トレーダーruka
トレーダーruka通常(コロナ前)
平均して「全雇用の±0.2%程度」の修正
例えば年間雇用200万人増なら、修正は数万人〜数十万人規模で収まる
大きくても30〜40万人程度の増減
現在のアメリカの雇用環境をどう見るか
足元の雇用統計を俯瞰すると、すでに減速トレンドに入っていることは明らかです。
5月・6月で大きく落ち込み、7月・8月も低水準のまま横ばい。若年層(16〜24歳)の失業率は10.5%に達し、パンデミック以来初めて2桁台を記録しました。
労働市場の構造変化も見逃せません。
- サービス業や小売業での雇用創出が弱まっている
- 製造業でも新規投資が減り、求人が伸び悩む
- 一方でテック企業は採用を絞り込み、AIや自動化が雇用機会を削っている
表面的には「まだプラス雇用」と見えますが、質的にも量的にも雇用が細っているのが実態です。
筆者のまとめ
今回の年次改定は、過去に例を見ない大幅修正であり、軽視してはいけない出来事だと思います。為替市場では一時的にドル円が反発していますが、これは「円の弱さ」によるもので、ドルの信用そのものは確実に下落していると見ています。
雇用が悪化すれば、次に訪れるのはリセッション。
経済がクラッシュするのは歴史的にも避けられないサイクルです。
今回の91万人の過剰計上は、トランプ大統領就任前のデータであり、今後より正確な数字が出てくる可能性はありますが、すでにアメリカという国の統計への信頼は大きく揺らいでいるのではないでしょうか。
「働く人が少ない」という事実は、消費の縮小や生産性の低下を通じてGDPを押し下げます。関税で一時的に補ったとしても、土台となる雇用が弱ければ経済の持続力は削がれていきます。
さらに問題なのは、**都合のいい数字だけを切り取って公表する“いやらしさ”**です。良い時は良い数字を強調し、悪い時だけ本当の数字を出す…。これが基軸通貨国アメリカの姿だとしたら、信用失墜は避けられません。
今後、CPIやPPIなどの経済指標にも同じような「修正リスク」が潜んでいます。短期的な相場の反発に惑わされることなく、歪んだ統計の裏側を読み解き、慎重に相場と向き合うべき局面に来ていると感じます。
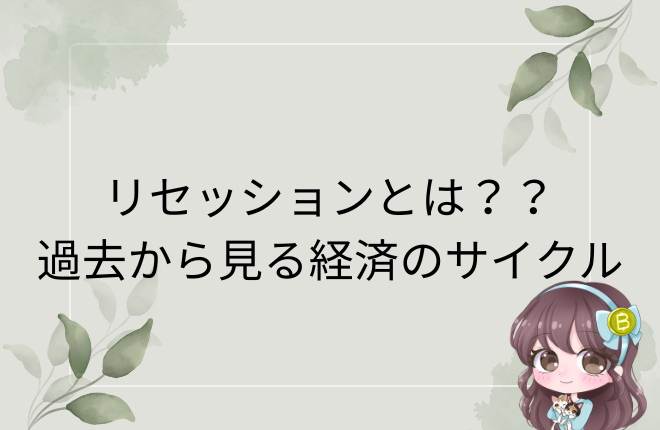
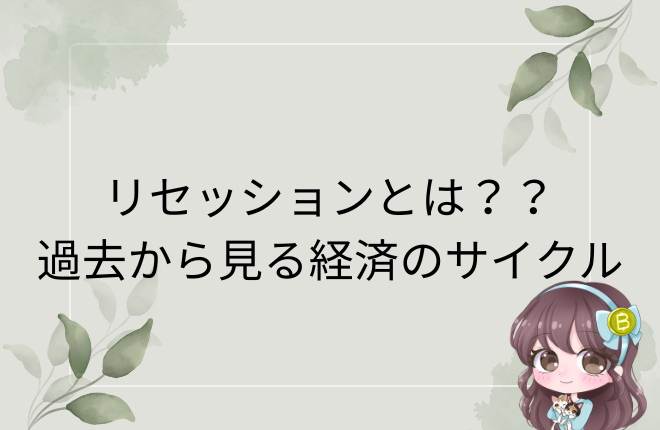
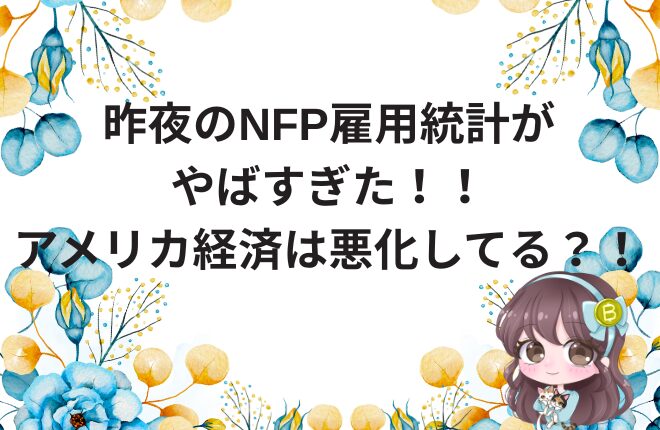
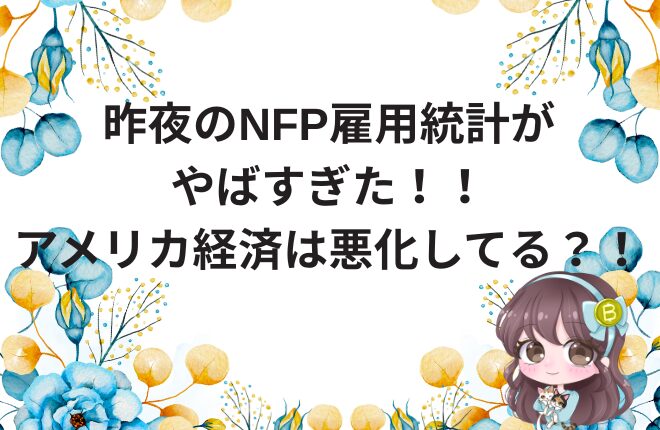
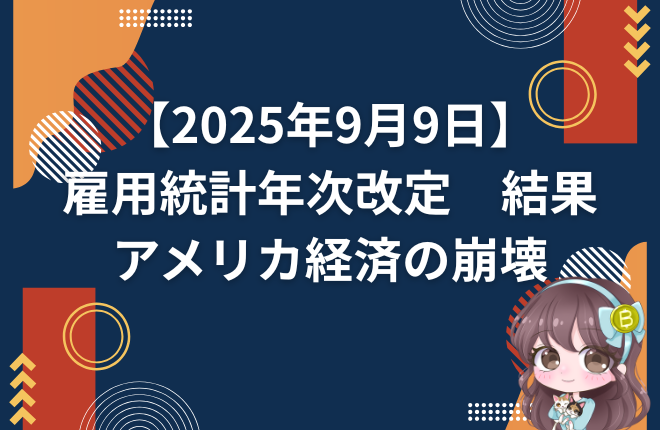
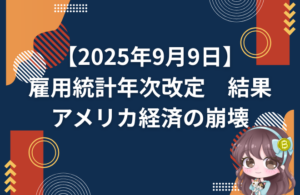
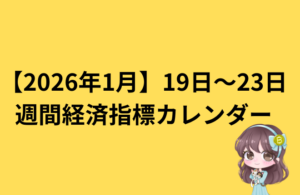
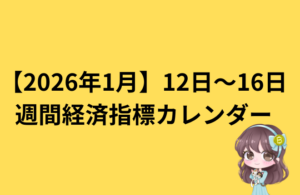
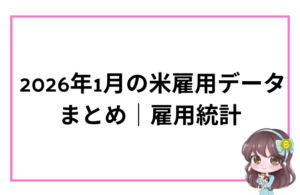
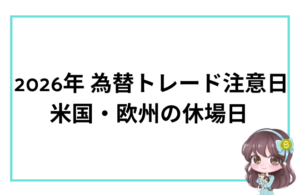
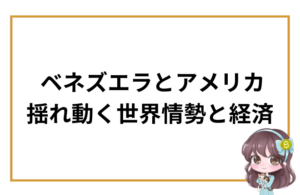
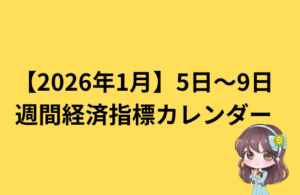
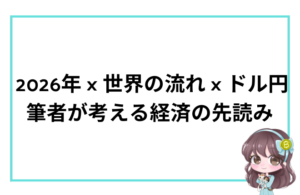
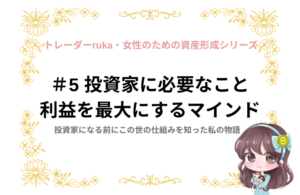
コメント